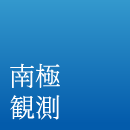「南極地域観測将来構想 新たな南極地域観測事業のあり方2018」中間報告を公開
2018年7月20日
国際地球観測年(1957-1958年)を契機に開始された我が国の南極地域観測事業では、これまで昭和基地やドームふじ基地、あるいは南極観測船「しらせ」を舞台に数々の科学的成果を上げてきました。1977年からは、4〜6年を一区切りとする中期的な計画を基に、各年度の実施計画を立案・実施してきており、現在は、2016-2022年の6年計画の枠組みで、第Ⅸ期計画を進めています。
前身の国立科学博物館の時代から実施機関として南極地域観測事業の中核を担ってきた国立極地研究所では、現南極観測船「しらせ」の就航(2009年)にあわせ、2008年に10年先の南極地域観測事業を見据えて「新たな南極地域観測事業のあり方-新観測船時代のビジョン-」を策定し、長期的な視点により第Ⅷ期、第Ⅸ期計画に取り組んできましたが、当初想定した10年が経過し、南極地域観測事業や学術・科学技術を取り巻く社会的、国際的な状況にも変化が生じています。
そこで、国立極地研究所では、時代に沿った新たな南極地域観測事業の将来構想を検討するため、2017年10月に所内の南極観測委員会の下に南極観測将来構想タスクフォースを設置し、南極観測センタースタッフと若手研究者を中心としたメンバーで計24回の会合、2回のワークショップ(うち一回は公開で実施)を重ね、2034年頃と見込まれる次期南極観測船就航を睨んだ将来構想の検討を進めてまいりました。
この度、より多くの皆さまの研究ニーズやアイディアを構想に盛り込んでいくため、2018年7月31日に開催する「南極観測シンポジウム2018」に併せて、中間報告という形で現時点の構想を公開することといたしました。本報告を基礎に、シンポジウムで新たに提案されるサイエンスの方向性や、本報告に対するご意見を踏まえ、2018年秋を目途として最終的な報告をまとめる予定です。
本報告が皆さまの目に留まり、最終報告までの間に、より多くの皆さまから多様なご意見をいただけることを期待します。
国立極地研究所
南極観測将来構想タスクフォース
委員長 野木義史