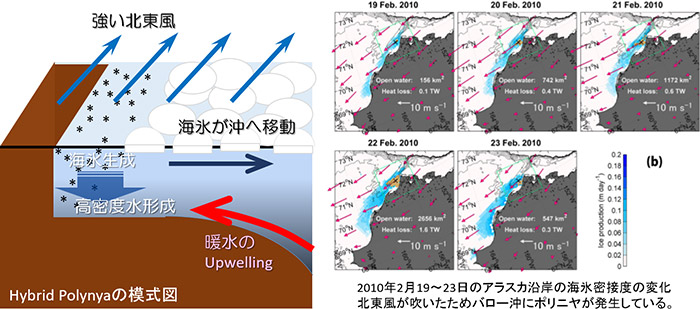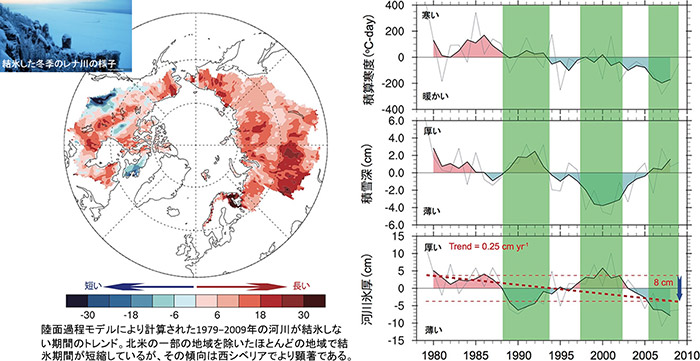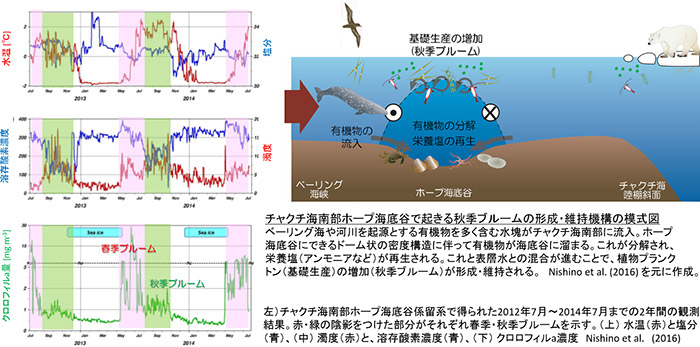平成27年度成果
国際共同研究推進:テーマ4
北極海洋環境観測研究
実施責任者:菊地 隆(海洋研究開発機構)
活動実績
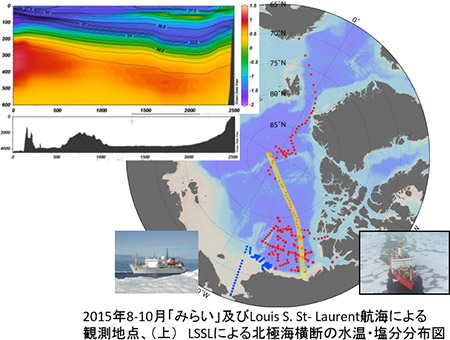
研究成果の公表
これまでの観測・解析結果を取りまとめた結果、査読付き英文誌に20本の論文(関連する他の予算(GRENE北極・科研費・運営費交付金など)による成果を含む)を発表した。
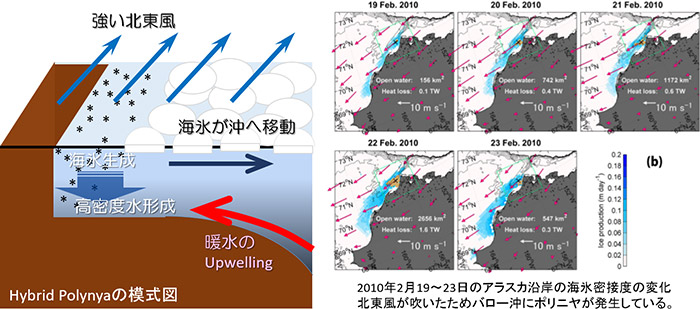
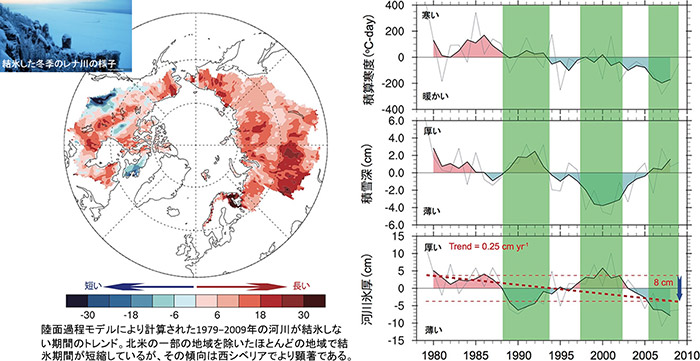
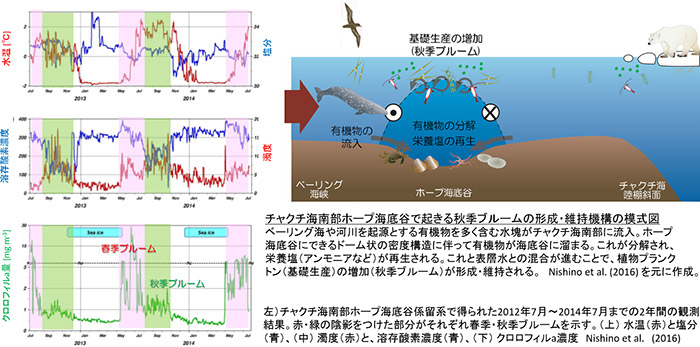
実施責任者:菊地 隆(海洋研究開発機構)
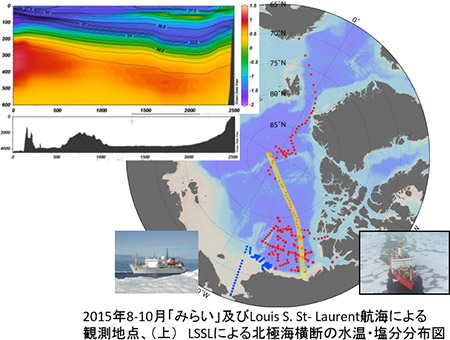
これまでの観測・解析結果を取りまとめた結果、査読付き英文誌に20本の論文(関連する他の予算(GRENE北極・科研費・運営費交付金など)による成果を含む)を発表した。