気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、2019年に「変化する気候下での海洋・雪氷圏に関する特別報告書」を発表し、海洋・雪氷圏が今後の全球的な気候変動の予測に重要な要素であることを指摘しています。IPCCでも取り上げられているように、地球温暖化をはじめとする地球環境問題において、氷床を有する南極と北極の両極域での研究観測の重要性は、ますます高まっています。南北両極域の研究観測の中核実施機関である、情報・システム研究機構国立極地研究所の役割も重要になってきています。その中で、地球規模の視点を持った両極域の研究観測を進め、国際的にも着実に成果をあげていく必要があるとともに、両極域の研究観測の重要性を広く社会に伝える事も求められています。加速化する地球温暖化に対して、今後の地球環境の変化を知る鍵となる極地の観測研究を行う研究所として、過去から現在の北極と南極の様々な時間・空間スケールの変動を明らかにし、地球環境の将来予測をより確かなものにしていきたいと考えています。
国立極地研究所は、1973年に設置された「極地の観測と総合的研究を行う」ことを目的とした大学共同利用機関、すなわち国内共同研究や国際共同研究を通じて全国の大学の研究力強化に資するための研究機関です。研究対象が極域を中心とする地球規模の環境・変動ですので、国際協力が必要不可欠となっています。国際学術会議(ISC)傘下のSCAR(南極研究科学委員会)、IASC(国際北極科学委員会)、SCOSTEP(太陽地球系物理学科学委員会)、SCOR(海洋研究科学委員会)などの学術組織の枠組みで各国と連携した観測研究を行いつつ、世界最先端の「極地発」のサイエンスを追求しています。
南極観測では、南極地域観測計第X期6か年画(令和4年度~令和9年度)において、「過去と現在の南極から探る将来の地球環境システム」を重点テーマとし、ドーム基地での最古級のアイスコア掘削や、「しらせ」集中的な海洋観測等が進められています。また、北極域では、北極域研究加速プロジェクト(ArCS II)(令和2年度~令和6年度)が現在実施されていますが、次期プロジェクトに向けて、今後の更なる発展および新たな研究観測の展開を検討する時期となっています。これらの観測研究事業を推進して、極地に関する観測研究を総合的に行う全国唯一の研究所としての役割を果たす国立極地研究所の活動に、ぜひ皆様方のご理解とご支援を賜りますようよろしくお願いいたします。
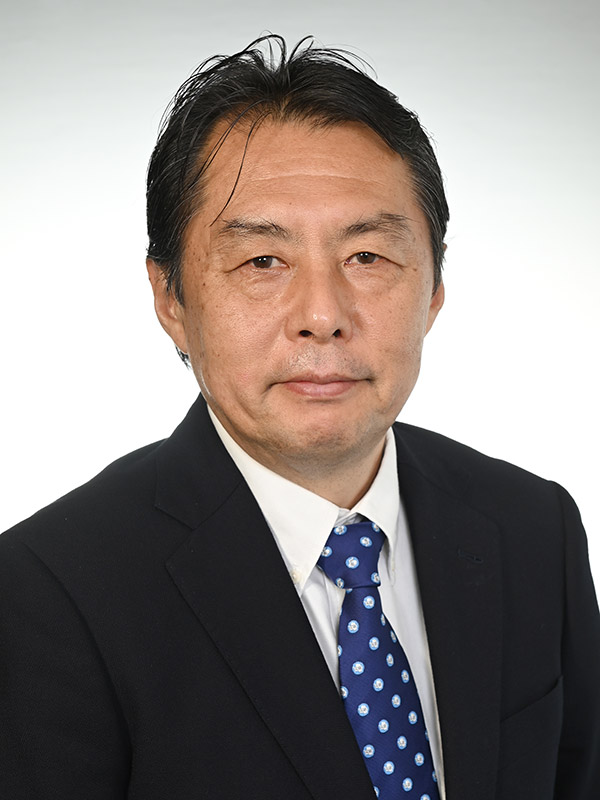
国立極地研究所長 野木義史
Copyright © National Institute of Polar Research All rights reserved.